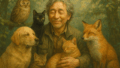森下悠一は、58歳。大手印刷会社に勤め、部長職を長らく務めたが、数年前、会社の合理化の波に押されて早期退職を余儀なくされた。送別会も形式的なもので、仲の良かった後輩たちも、妙に気を遣うような表情で頭を下げるばかりだった。
「部長、長い間お疲れさまでした。」
誰もがそう言って、乾いた笑いを交わした。
退職後の森下は、一人暮らしの自宅で静かな日々を送っていた。朝はコンビニでコーヒーを買い、公園を歩き、図書館で雑誌を読み、昼はスーパーで弁当を買う。夜はテレビをつけて、誰のいない部屋で食事をとる。
一日誰とも話さず終わる日も、珍しくなかった。
誰かに会いたいと思う瞬間も、なくはなかった。だが、その「誰か」が、思い浮かばない。
独身だった。
結婚をしなかった理由は、よく聞かれた。だが、本人にもよくわからなかった。若い頃は仕事に夢中で、気づけば周囲は結婚していた。出会いがなかったわけではない。ただ、自分の人生に誰かを迎え入れる勇気がなかったのかもしれない。
「自分は人を幸せにできない」と、どこかで信じていた。
一度だけ、真剣に結婚を考えた女性がいた。彼女は、同じ会社の営業部で働いていて、面倒見がよく、笑うと目尻がきゅっと下がる人だった。何度か食事を重ね、自然と付き合うようになった。
36歳の春、彼女がぽつりと言った。
「子ども、欲しいな。そろそろ、考えないとだよね。」
悠一は黙って、酒を飲んだ。返事はしなかった。
その数日後、彼女は別れを切り出した。
「悠一さんは、きっと私のこと嫌いじゃないんだろうけど、自分の未来に私を入れてない気がする。」
正直、否定できなかった。自分が何を求めているのか、自分でもわかっていなかった。
以来、誰とも付き合わなかった。
50を過ぎて、部下たちの結婚式に招かれるたび、少しだけ胸が痛んだ。だが、それもいつしか慣れてしまった。
そんなある日、一通の手紙がポストに届いた。
「森下様、このたび中学の同窓会を開くことになりました。よろしければ、ぜひご参加ください。」
懐かしい名前が差出人に記されていた。田中美咲は中学時代、となりの席に座っていた彼女。明るく、誰にでも優しい女の子だった。
久しぶりに行った同窓会は、思いのほか楽しかった。何十年ぶりかの再会に、皆が少し照れながらも話に花を咲かせた。見た目は変わっていても、声や表情は昔のままだった。
美咲も来ていた。少しやつれた様子だったが、相変わらず柔らかな笑顔だった。
「悠一くん、全然変わってないね。今、どうしてるの?」
「会社辞めたよ。今は、まあ、のんびりしてる。」
「私もひとり暮らしよ。離婚して、息子はもう就職したから。」
二人は、話が弾んだ。中学の頃のいたずら、先生の癖、放課後の寄り道。あっという間に時間が過ぎて、連絡先を交換し、別れた。
それから月に一度、二人で食事をするようになった。恋人でも、友達でもない。だが、久しぶりに人と「時間を分け合う」という感覚が、悠一には心地よかった。
ある夜、美咲が言った。
「悠一くんって、昔から人の影に隠れてる感じだったよね。優しいけど、自分のことあんまり出さない。」
図星だった。
「だから、昔、ちょっと好きだったけど、あきらめたの。」
悠一は、何も言えなかった。
その言葉を聞いて、ずっと胸の奥に押し込んでいた感情が、ゆっくりと浮かび上がってきた。
寂しかった。誰にも頼らず生きてきて、今さら「誰かを求める」ことが怖かった。
それでも、美咲と過ごす時間は、確かに自分を変え始めていた。
春が来た頃、美咲から連絡があった。
「実はね、再婚することにしたの。」
驚いたが、納得もした。彼女はずっと、一人でがんばってきた。誰かに支えられる人生を、ようやく手に入れたのだ。
「悠一くんと話す時間、大好きだったよ。本当にありがとう。」
その言葉は、確かに嬉しかった。けれど同時に、胸の奥が静かに冷たくなった。
家に帰ると、テレビがつけっぱなしだった。誰もいない部屋に、ワイドショーの騒がしい音が響いていた。
ソファに座って、天井を見つめる。
結局、自分の人生は、誰の人生でもなかった。
誰かを傷つけなかった代わりに、誰かの人生に深く関わることもなかった。安全な道を選び続けた結果、誰の記憶にも残らない人生になっていた。
スマホを開いても、通知はない。LINEは、最後のメッセージが2か月前の美咲からの「元気?」だった。
森下悠一、58歳。家族はいない。頼る人もいない。
しかし、後悔というほどの激しい感情もない。ただ、淡々と時が過ぎるのを感じる。
孤独は、静かに、確かに人生を蝕んでいく。
これが、自分の選んだ人生の末路なのだと、彼は受け入れようとしていた。
夜、寝る前に窓を開けた。遠くで犬の鳴き声がした。冷たい風がカーテンを揺らす。
誰の声も聞こえない静かな部屋で、悠一は布団に入り、目を閉じた。
明日もきっと、同じような一日がやってくるだろう。
そして彼は、それを誰にも知らせることなく、ただ静かに受け入れながら、生きていた。