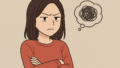陽がまだ昇りきらない早朝。川沿いのジョギングコースを、一人の女性が黙々と走っていた。額に汗を浮かべ、無表情で足を運ぶその姿は、まるで機械のようだった。
彼女の名は水原 梨花(みずはら りか)、28歳。中学から陸上競技一筋で、大学では日本代表候補にまでなった実力者だ。しかし、五輪出場の夢を目前に控えた24歳のとき、肉離れからの故障が重なり、表舞台から姿を消した。
「引退なんて、私にはまだ早い」
その言葉通り、梨花は競技をやめなかった。スポンサーも離れ、コーチもいなくなったが、自主トレーニングを続け、再起を目指していた。昼は陸上用品店のアルバイト、夜はジムとトラック。休日も返上で走り続け、友人との交流も、恋愛も、すべてを犠牲にしてきた。
だが、現実は残酷だった。
年齢的にもタイムが伸び悩み、若手選手との力の差は広がる一方。出場できる大会も減り、地方大会でさえ一次予選落ちという結果が続いた。
「まだ、やれる……まだ、足りないんだ……」
梨花はそう言い聞かせていたが、自分でも気づいていた。体はもう限界だった。膝には慢性的な痛みが走り、朝起きるたびに脚が重かった。だが、彼女の頭には常に「栄光」の幻影がこびりついていた。
ある日、大学時代の親友・沙耶から久しぶりに連絡が来た。
「久しぶりに会わない? ずっと心配してたんだよ」
梨花は渋々ながらも沙耶と会うことにした。待ち合わせ場所のカフェで現れた沙耶は、結婚指輪を光らせ、妊娠中のふっくらしたお腹を優しく撫でていた。
「梨花、元気にしてた? 今は何してるの?」
「……走ってるよ、まだ。来年の大会を目指してる」
「そっか……でも、梨花、もう無理しなくてもいいんじゃないかな? 体、心配だよ」
その言葉に、梨花はピクリと眉を動かした。
「私には、走ることしかないから」
「そう思ってるの、梨花だけかもよ。周りは、もう――」
「もういい」
梨花は会話を遮り、席を立った。胸の奥で何かがひび割れたような音がした。
それから数日後の朝。いつもと同じようにジョギングに出た梨花は、突然、右膝に鋭い痛みを感じた。足が止まり、崩れ落ちる。
「……あれ?」
立ち上がれない。激痛が走る。救急車で運ばれ、MRI検査の結果、右膝の靭帯損傷と診断された。医師ははっきり言った。
「この状態で無理に走り続けていたら、歩けなくなる可能性もありました。今すぐ治療とリハビリに専念すべきです」
梨花は呆然と天井を見つめた。目を閉じても、トラックの風、歓声、ゴールテープの感触だけが頭の中をよぎる。
「それを……奪うの?」
誰に向けた言葉か分からない問いを、声にならないまま飲み込んだ。
ベッドの上で動けぬまま、梨花はふと、スマホに溜まったメッセージを開いた。大会関係者からの連絡は途絶えて久しく、今残っているのは、かつての仲間やコーチからの「心配」の言葉だけ。
「もういい加減、諦めなよ」
そんなメッセージを見つけ、指が震えた。悔しさ、情けなさ、そして、ぽっかりと空いた心の隙間。勝利のために削り続けた時間の果てに、自分には何が残っているのだろう。
彼女の競技人生は、終わりの兆しを見せ始めていた。
「水原さん、少しずつでいいので、右脚に体重をかけていきましょう」
リハビリ室に響く理学療法士の声。梨花はその言葉に従い、ゆっくりと歩行器を押しながら、一歩一歩を踏み出した。競技人生で何万回と走ってきたはずの足は、まるで他人のもののようにぎこちなく、重たかった。
怪我から1か月。運ばれたときの激痛が嘘のように消えた代わりに、彼女の中にはぽっかりと穴が空いていた。
「私、なにしてるんだろう」
競技から離れ、日々のルーティンが崩れた今、梨花は自分の存在価値すら分からなくなっていた。走ることを辞めた自分に、果たして何が残っているのか。答えはなかなか見つからなかった。
退院後、しばらくは自宅療養を続けていたが、心身の焦燥感から、梨花は沙耶に再び連絡を取った。
「ごめん、前にあんな言い方して……今、少しだけ話せるかな?」
電話越しに沙耶の声が明るく響いた。
「うれしい! もちろん。家においでよ。赤ちゃん、もうすぐ産まれそうなんだ」
沙耶の家に足を踏み入れたとき、梨花は言葉を失った。暖かな香り、家族の写真、キッチンから漂う煮込み料理の匂い。自分とは正反対の、けれど否応なく「幸せ」と感じられる空気が、そこにあった。
「梨花、こっちも大変だけどさ、すごく充実してるよ。命を育ててるって感覚、なんていうか、自分の存在が誰かのためにあるって実感できるの」
その言葉に、梨花はハッとした。
自分は、誰のために走っていたのだろう。勝利のため? 自分の夢のため? それとも、過去の自分を裏切らないため?
翌日から、梨花は一日一日を少しずつ変えることにした。朝はゆっくりコーヒーを淹れ、ストレッチ代わりに軽いヨガを取り入れ、日記をつけるようになった。
そしてある日、かつての恩師から「スポーツ少年団のコーチを探している」という連絡が届いた。
「水原、お前の経験、無駄にはならないよ。子どもたちに走る楽しさを教えてやってくれないか」
最初は迷った。もう一度スポーツと向き合うことが、過去の栄光と挫折を思い出させるのではないかと怖かったからだ。
しかし、グラウンドに立ち、無邪気に走り回る子どもたちを見た瞬間、梨花の中の何かがほどけた。
「フォームはそれでいいよ! でも、肩の力を抜いて、もっとリラックスしてごらん」
久しぶりに発する指導の声。かつての自分に言い聞かせるようなその言葉に、梨花の顔には自然と笑みが浮かんでいた。
競技者としてではなく、導く者として――彼女は再び「走る」意味を見出し始めたのだ。
それから1年。梨花は地域の陸上クラブで正式な指導者となり、子どもたちや学生たちにフォームやメンタル、食事管理まで幅広く教えるようになっていた。SNSでは「鬼コーチ」として少しだけ話題になり、講演依頼や雑誌の取材も来るようになった。
「先生、なんでそんなに詳しいの?」
「昔ね、私も本気で世界を目指してたんだよ。でも、色んなことがあってね……」
そう語る彼女の目には、もう未練も虚しさもなかった。あるのは、スポーツへの純粋な愛情と、教えることへのやりがい。
だが、その夜、彼女はふと一人の少女に呼び止められる。
「先生、私、大きくなったらオリンピック出たい。どうすればなれるかな?」
梨花はしばらく黙って空を見上げた。そして、静かにこう答えた。
「誰かに勝ちたいとか、金メダルが欲しいって気持ちも大事だけどね、それだけじゃだめ。自分自身を大事にして、ちゃんと心と体の声を聞ける人じゃないと、きっと途中で壊れちゃうから」
少女はきょとんとした顔で「わかったような、わかんないような」と笑った。
それを見て、梨花もふっと微笑んだ。
梨花は、今でも走ることはある。ただし、それは誰かに勝つためではなく、自分自身のために。風を切る感覚、地面を蹴る感触、呼吸のリズム。それらすべてが、今の彼女にとっては「生きている実感」そのものだった。
スポーツに打ち込みすぎたあの頃。すべてを犠牲にして突き進んだ道の先に、「栄光」はなかったかもしれない。
だが――
あの道を通ったからこそ、今の彼女がある。
そして彼女は今日もまた、小さな背中に向けて、全力で声を張り上げる。
「いいぞ、その調子! 自分を信じて、走り抜けろ!」