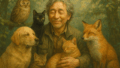人間不信だった。
誰の言葉も信じられなかったし、優しくされると「どうせ裏があるんでしょ」と心の中で毒づいた。家族にすら信用できなかったのだから、他人に心を許すなんて到底無理だった。
そんな自分が、人を好きになるなんて——思ってもいなかった。
大学三年の春、アルバイト先のカフェに、千尋(ちひろ)という女性が新しく入ってきた。年齢は一つ上。物静かで、丁寧で、少し抜けたところもあって、第一印象は「話しかけづらい人」だった。
最初のうちは、必要なことしか話さなかった。
「そこ、コーヒー豆のストックお願い」
「はい……あの、どこに置けば?」
「奥の棚でいい」
それだけで終わる会話だったのに、ある日、ふいに千尋がこう言った。
「あなた、人と距離、取ってるよね」
心臓が跳ねた。
図星すぎて、言葉が出なかった。
「悪く思わないで。私もそうだから、なんとなく分かるだけ」
彼女の表情には、敵意も好奇心もなかった。ただ、静かな共感だけがあった。
その日から、少しずつ、彼女と話すようになった。
雨の日は「寒いね」と言い合い、忙しい日には「お疲れさま」と笑い合った。そんな他愛ないやり取りが、なぜか心地よかった。
でも、自分の中には壁があった。
彼女に興味はある。でも、踏み込むのが怖い。もし、また裏切られたら? もし、心を開いた瞬間に傷つけられたら? そう思うと、一歩が踏み出せなかった。
ある日、バイト終わりに千尋が「コーヒー、飲んでいかない?」と声をかけてきた。
「私の家、近いの。もしよかったら、だけど」
一瞬、躊躇した。でも、その瞳が真剣で、やっぱり嘘がなさそうで——気づけば、うなずいていた。
彼女の部屋は小さなワンルームで、本と観葉植物が整然と並んでいた。部屋には静かな音楽が流れていて、どこか安心感があった。
「これ、自分で焙煎したの。ちょっと苦いけど、美味しいよ」
そう言って差し出されたマグカップからは、ふんわりと優しい香りが立ちのぼっていた。
ふと、棚にあった一冊の本に目が止まった。
『人を信じるということ』
思わずつぶやいた。
「……皮肉だな、俺が読むべきかも」
千尋は少し微笑んで言った。
「それ、私も思ってた。自分のこと、信じるのが一番難しいけどね」
そのとき、不意に聞いてみた。
「千尋さんって……人を、信じられる?」
彼女は少しだけ目を伏せた後、答えた。
「今は……信じたい人が、いる」
その言葉に、胸がきゅっと締めつけられた。
それは、自分のことかもしれない——という希望と、それが勘違いだったら、という恐怖。
言葉にできないまま、時間だけが流れた。
それから一ヶ月ほどして、ある出来事があった。
カフェで、客とトラブルになった。
客が過剰に怒り、スタッフを怒鳴りつけた。たまたまそれに巻き込まれ、自分が責められた。
「申し訳ございません」と何度も頭を下げるうちに、涙が出そうになった。
そのとき、千尋が間に入った。
「彼は悪くありません。こちらの案内ミスです。責任は私にあります」
毅然とした声だった。
その後、客は不満を残して帰っていった。
スタッフルームで、思わず口にした。
「……なんで、庇ってくれたの?」
千尋はコートを脱ぎながら、言った。
「当たり前でしょ。あなたが傷つくの、見たくなかったから」
その一言で、なにかが決壊した。
張り詰めていた壁が崩れ落ちて、涙がこぼれた。
この人になら、心を見せてもいいかもしれない。
生まれて初めて、そう思った。
それからの関係は、少しずつ、でも確実に深まっていった。
手をつなぐのも、時間がかかった。
キスをするまで、半年近くかかった。
それでも千尋は、一度も急かさなかった。
「あなたのペースでいいから」と微笑むたびに、世界が少しだけ優しくなる気がした。
人間不信だった自分が、今では、彼女に今日の出来事を話すのが楽しみになっている。
「人って、変われるんだね」と言ったとき、千尋は言った。
「変わったんじゃないよ。もともと、優しいだけ。誰かにそれを信じてもらえなかっただけ」
その言葉に、涙がにじんだ。
信じることは、怖い。
でも、誰かを信じられたとき人生はこんなにも、温かい。